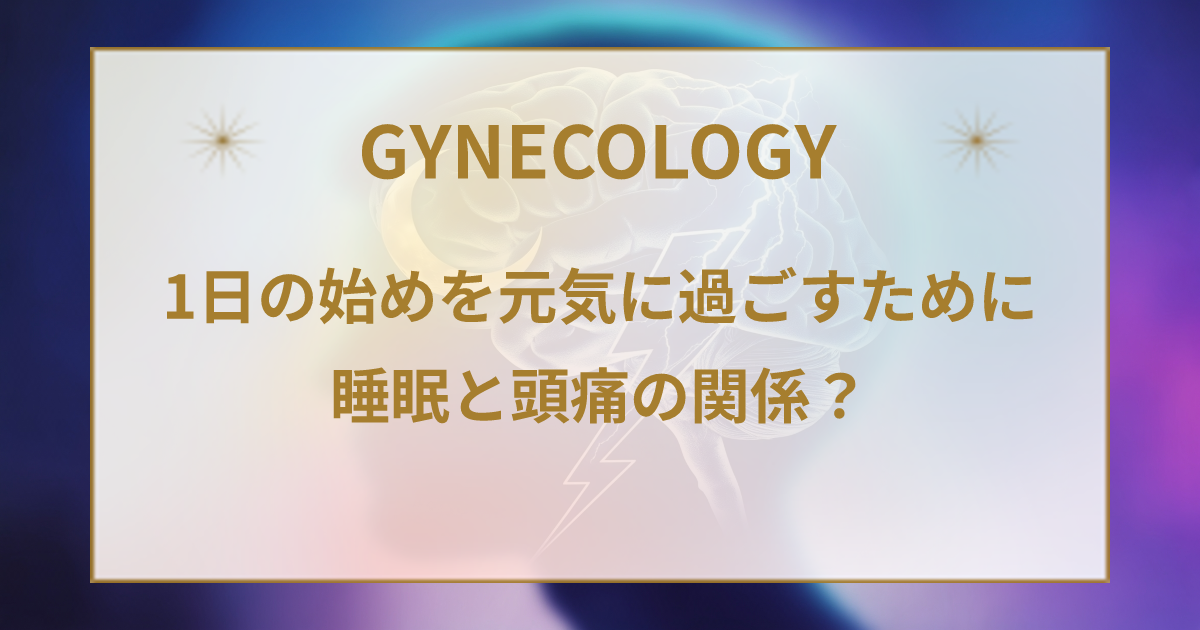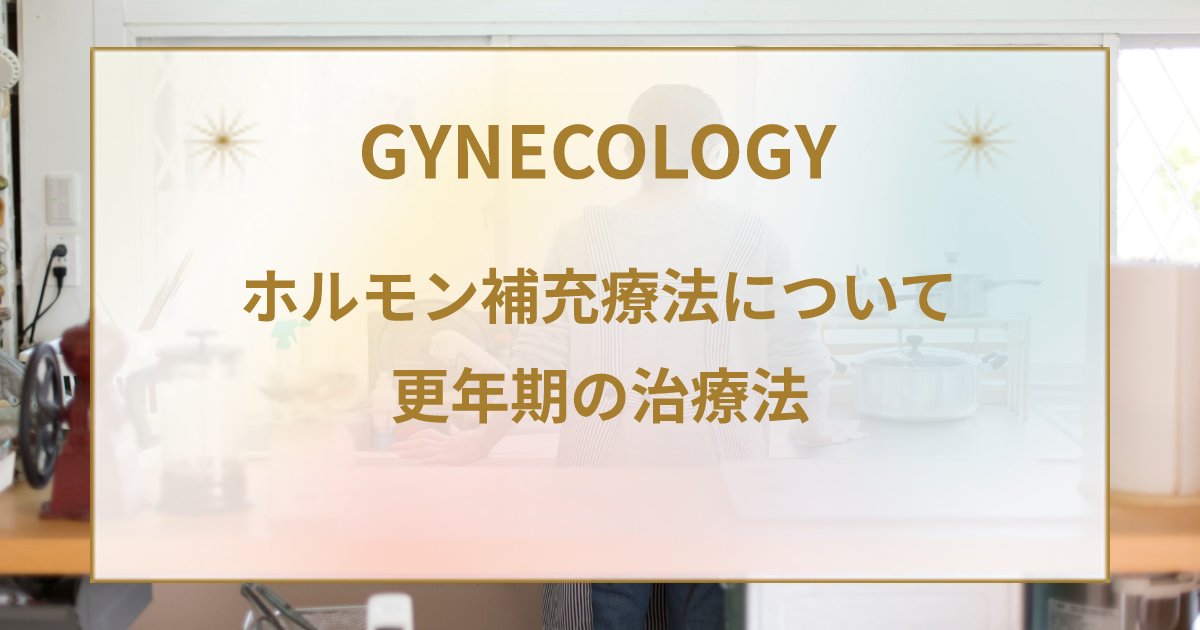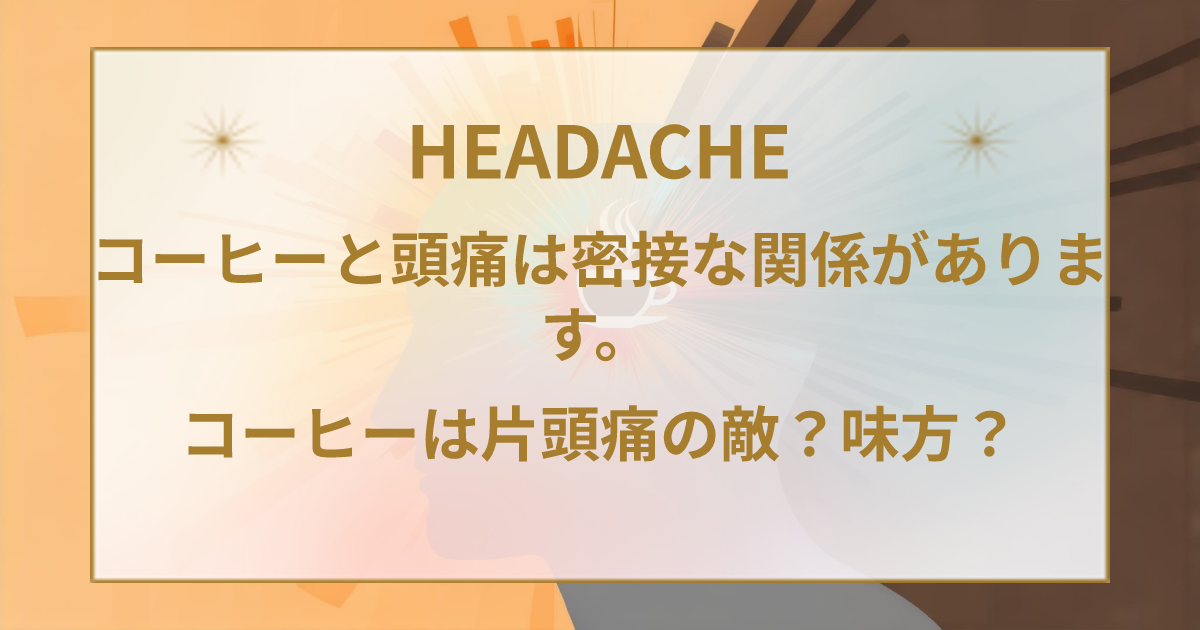
コーヒーは片頭痛の味方?敵?関係性を解説
コーヒーを飲むと頭痛が治まる、でも逆に悪化することも?実はコーヒーと片頭痛の関係は複雑です。
多くの人が毎日の生活に欠かせないコーヒーですが、片頭痛持ちの方にとっては、その効果は人それぞれ。血管を収縮させるカフェインは、一時的に頭痛を和らげる一方で、反動的に血管が拡張し、頭痛を引き起こすこともあるのです。
この記事では、コーヒーが片頭痛に与える影響を徹底解説します。カフェインのメカニズムから、コーヒーの種類、飲み方、そしてコーヒー以外の片頭痛予防策まで、分かりやすく解説します。1日に飲む適切な量や、片頭痛を悪化させないための工夫なども紹介。コーヒーを愛する片頭痛持ちのあなたも、ぜひ読んでみてください。もしかしたら、今よりも快適な毎日を送れるヒントが見つかるかもしれません。
目次
コーヒーが片頭痛を誘発するメカニズム
コーヒーに含まれるカフェインは、血管を収縮させる作用があります。血管が拡張していることが片頭痛の最中には、コーヒーを飲むと一時的に頭痛が和らぐことがあります。これは、まるで風船がしぼむように、拡張した血管が収縮することで痛みが軽減されるためです。
しかし、この効果は一時的なもの。多くカフェインを取りすぎると、反動で血管が拡張し、それが片頭痛の痛みを悪化させてしまいます。これは、ゴムを伸ばしてすぐに戻すと元に戻るようなイメージです。
また、毎朝コーヒーを飲む習慣のある方が、ある朝コーヒーを飲まなかったとします。すると、カフェインの摂取が日課の人はカフェインを摂取しないことによる離脱症状で、頭痛に襲われることがあります。
毎朝コーヒーを飲んでいて、飲み忘れた日に片頭痛が起こるという患者さんは多くいらっしゃいます。週末にはカフェインを摂取しないため、週末になると頭痛が起こる、という方もいらっしゃいます。
コーヒーの成分と片頭痛との関連
コーヒーに含まれる成分の中で、片頭痛に最も影響を与えるのはカフェインです。カフェインは少量であれば、片頭痛の痛みを和らげる効果が期待できます。
しかし、カフェインを過剰に摂取すると、先ほど説明したように血管が反動的に拡張し、片頭痛を誘発する可能性があります。
また、カフェインには利尿作用があり、体内の水分を排出してしまうため、脱水症状を引き起こす可能性があります。脱水症状も頭痛の誘発因子の一つです。体内の水分が不足すると、頭蓋骨内の血管や神経を圧迫する可能性が報告されています。また脱水による頭痛は、片頭痛の方はそうでない方と比べて少しの脱水でも頭痛を起こしやすいことが言われています。
コーヒーにはカフェイン以外にも、ポリフェノールなどの成分が含まれています。この成分も血管を拡張させる作用があり、片頭痛に影響を与える可能性があるため、注意が必要です。
片頭痛の原因となる他の飲食物
コーヒー以外にも、片頭痛の誘因となる飲食物は様々です。チョコレートやチーズ、赤ワインなどは、血管拡張作用のあるチラミン(血管を収縮させ反動的に拡張する)やヒスタミンを含んでいます。これらの物質は、血管を広げる作用があり、片頭痛を引き起こす可能性があります。加工肉に含まれる亜硝酸塩も同様です。
例えば、赤ワインを飲んだ後に頭痛がする、という経験をしたことがある方もいるのではないでしょうか。これは、赤ワインに含まれるチラミンやヒスタミン、そしてアルコール自体が血管を拡張させる作用を持つためです。
また、人工甘味料や柑橘系の果物、ナッツ類なども、人によっては片頭痛の誘因となることがあります。食品添加物の中には、血管を拡張させる作用を持つものもあるため、加工食品の摂りすぎにも注意が必要です。
食事と片頭痛の関係は個人差が大きいため、食べたものと頭痛の有無、そして頭痛の程度を記憶していくことで、自分の片頭痛の誘因となる食べ物を特定し、対策を立てることができます。
一日の理想的なコーヒー摂取量
では、コーヒーは1日にどれくらいまで飲んで良いのでしょうか?一般的には、1日にコーヒーカップ2杯程度、カフェイン量でいうと約200mgまでと言われています。それ以上日々摂取している方は要注意です‼️しかし、これはあくまでも目安であり、個人差が大きいことを忘れてはいけません。少量のカフェインでも片頭痛が誘発される方もいます。
カフェインの過剰摂取は、片頭痛以外にも、動悸やめまい、吐き気、不眠などの症状を引き起こす可能性があります。まるで、エンジンを回しすぎるとオーバーヒートしてしまうように、体にも負担がかかってしまうのです。もしコーヒーを飲んだ後にこのような症状が出た場合は、摂取量を減らすなどしましょう。
コーヒーの種類が片頭痛に与える影響
片頭痛持ちの方にとって、コーヒーは複雑な存在です。毎朝の目覚ましに、午後の休憩に、ついつい手が伸びてしまう方も多いのではないでしょうか。しかし、実はコーヒーの種類によって、片頭痛への影響が大きく変わることをご存知ですか?コーヒーの種類によって片頭痛への影響も変化するのです。この章では、コーヒーの種類による片頭痛への影響について、カフェイン量やコーヒー豆の種類、インスタントかレギュラーかといった様々な要因を紐解きながら、詳しく解説していきます。自分に合ったコーヒーの選び方や飲み方のヒントが見つかるかもしれません。
カフェインの含有量が高いコーヒーのリスク
特に、エスプレッソや濃いめのドリップコーヒーはカフェイン含有量が高いため、片頭痛持ちの方は注意が必要です。私の外来にも、毎日何杯もエスプレッソを飲んでいて、慢性的な片頭痛に悩まされている患者さんがいらっしゃいました。エスプレッソは少量ながらもカフェインが凝縮されているため、少量でも影響が出やすいと言えるでしょう。1日に何杯もコーヒーを飲む習慣がある方は、カフェインレスコーヒーに切り替えたり、ハーブティーなどのノンカフェイン飲料に変えることを検討してみてください。カフェインレスコーヒーはカフェインが90%以上除去されているため、カフェインの影響を最小限に抑えることができます。
コーヒーの種類 | カフェイン含有量(mg/100ml) |
|---|---|
エスプレッソ | 200 |
ドリップコーヒー | 60 |
インスタントコーヒー | 60 |
カフェインレスコーヒー | 1-2 |
デカフェの効果とリスクについて
カフェインを摂取したくない、または摂取を控えたい片頭痛持ちの方にとって、デカフェは魅力的な選択肢です。デカフェは、カフェインを97%以上除去したコーヒーなので、カフェインによる片頭痛の誘発や悪化のリスクを軽減できます。
しかし、デカフェだからといって、完全に安全というわけではありません。「デカフェ=カフェインゼロ」と勘違いしている患者さんも多くいらっしゃいますが、デカフェにも少量のカフェインは残っています。そのため、大量に摂取すればカフェインの影響を受ける可能性はゼロではありません。また、カフェイン以外のコーヒー成分、例えばタンニンやクロロゲン酸などが片頭痛の引き金になる可能性も否定できません。
デカフェを選ぶ際は最初は少量から試してみて、自分の体に合うかどうかを確認することが大切です。デカフェでも片頭痛が悪化する場合は、他のノンカフェイン飲料に切り替えることを検討しましょう。
片頭痛予防に役立つルーチン
片頭痛は、生活習慣とも深く関わっています。規則正しい生活を送ることは、片頭痛予防の第一歩と言えるでしょう。
規則正しい生活:睡眠不足や不規則な食事は、自律神経のバランスを崩し、片頭痛の誘発因子となります。人間の体は、体内時計によって睡眠や覚醒、ホルモン分泌、体温調節などをコントロールしています。この体内時計のリズムが崩れると、様々な不調が現れ、片頭痛発作の引き金となる可能性があるのです。毎日同じ時間に寝起きし、3食きちんと食べるように心がけましょう。
- 適度な運動:軽いウォーキングやヨガなどの適度な運動は、ストレス解消や血行促進に効果があり、片頭痛予防にも繋がります。運動によって心身のリフレッシュ効果が得られ、ストレスホルモンの分泌が抑制されるため、片頭痛発作の予防に役立ちます。また、運動は血行を促進し、脳への酸素供給をスムーズにする効果も期待できます。
- リラックス:ストレスを溜め込まないことも、片頭痛予防には非常に重要です。ストレスは自律神経のバランスを乱し、片頭痛発作の引き金となる可能性があります。好きな音楽を聴いたり、アロマを焚いたり、ゆっくりとお風呂に入ったりするなど、自分に合ったリラックス方法を見つけ、心身のリフレッシュを図りましょう。
- トリガーを把握:片頭痛の誘発因子(トリガー)は人それぞれです。特定の食べ物や飲み物、強い光や音、匂い、気候の変化、睡眠不足、ストレスなど、様々なものがトリガーとなる可能性があります。自分にとって何がトリガーになっているのかを把握し、なるべく避けるようにすることで、片頭痛発作の頻度や強度を軽減できる可能性があります。食事日記や頭痛ダイアリーをつけることで、自分のトリガーを特定するのに役立ちます。
これらのポイントを参考に、ご自身の生活スタイルに合わせてコーヒーとの付き合い方を見つけてみてください。
頭痛でお悩みの方はお気軽にご相談を
頭痛は生活の質を著しく落とします。
中には昔から頭痛があり頭痛があることが当たり前となってしまい、頭痛の少ない生活を覚えていないため想像もつかない方もいるでしょう。
また頭痛に対して痛み止めを頻回に飲むことで気が付かずに薬物乱用頭痛に陥ってる可能性もあります。
頭痛でお悩みの方はまずはお気軽にご相談ください。頭痛を改善するサポートをいたします。